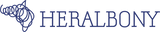ヘラルボニーの原点、るんびにい美術館の板垣崇志と語る命と覚悟「聴く美術館#21」

この春スタートした福祉実験カンパニー・ヘラルボニーの契約アーティストにフォーカスするポッドキャスト「HERALBONY TONE FROM MUSEUM〜聴く美術館〜」。
俳優・映像作家・文筆家として活躍する小川紗良さんと、ヘラルボニーの代表取締役社長の松田崇弥(たかや)が聞き手となり、アートに耳を澄ませながら、作品の先に見えるひとりの”異彩作家”の人柄や、これまでの人生に触れていきます。
最終回まであと1話となった今回のゲストは、ヘラルボニーの原点である岩手県花巻市のるんびにい美術館でアートディレクターを務める板垣崇志さん。"命を感じるアート"と評する異彩作家の作品を通して板垣さんが伝えたいこととは。ヘラルボニーへの想いと共にお話しいただきました。
#板垣さんが賭けたもの
小川:今回のゲストはどなたですか?
崇弥:ヘラルボニー創業のきっかけとなった、るんびにい美術館のアートディレクターをされている板垣崇志さんにお越しいただいてます。ヘラルボニーの前に「MUKU」というブランドを作ったときに、一番最初にプレゼンテーションをさせてもらったのが板垣さんでした。もう僕らが「こいつら誰だ」って感じのときから、ご一緒させていただいて、一番最初から応援してくださっている、ある種の創業者のひとりであると私が思ってるような方でございます。本日はよろしくお願いします。
小川:お願いします!
板垣さん:お願いします。板垣です。
小川:ということで、今日は板垣さんとリモートで繋がってます。今、岩手にいらっしゃるんですよね?
板垣さん:はい。
小川:板垣さんは、崇弥さんたちが初めてプレゼンに来られたときのことって覚えてますか?
板垣さん:はい、覚えてます。ヘラルボニー創業メンバーの一人で、大田さんという今もコアな役割を担われてる方がいらっしゃいまして、実は崇弥さん、文登さんとは高校時代の卓球のライバルでもあった方なんですけど。その大田さんが最初にアポの連絡をくださって、その後に崇弥さんと文登さんが美術館にいらっしゃったのが初対面でした。
小川:最初はどういうアポだったんですか?
崇弥:当時私は東京で働いていて、お盆に帰省したときに母親が「岩手県花巻のるんびにい美術館っていう、障害のある人たちが描いてる美術館がすごい」と兄の翔太も一緒に3人で行ったんですよ。当時、八重樫季良(やえがし・きよし)さんや佐々木早苗さんって作家さんの作品が並んでいて、なんてかっこいいんだろうと衝撃を受けて、何か自分たちのクリエーションとご一緒させていただいけないだろうかと思ったら、もういても立ってもいられなくて。「るんびにいタイ」というネクタイのブランドを作りませんかと企画書を書いて、飛び込み営業のようにプレゼンしに行きました。
板垣さん:うんうん。
小川:それは「MUKU」のときですよね?
崇弥:そうです。「MUKU」はたしか7年前ほどに立ち上げたブランドなので、プレゼンしにいったのは8年ほど前だと思います。
小川:板垣さん、そのネクタイを作りたいって話を聞いてどう思われましたか?
板垣さん:実は作品を製品化をしたいって申し入れは、崇弥さんたち以前にもあったんですね。崇弥さんたちの企画書は、まだこれから話し合って詰めていく必要がある要素はあるものの、すごくアピール力のある企画書を持っていらっしゃいました。企画書にはネクタイのイメージ画像も組み入れてあったのですが、その時点では、最終的に完成したネクタイとはだいぶイメージの異なる柄のものだったんですね。シンプルでオーソドックスな、パターンとして作品を利用するイメージビジュアルでしたので、その段階では企画内容自体に驚くということはなく、「なるほど、こういうものを作ろうとしてるんだな」という印象だったのですが、すごくよく考えられてて、地に足がついた、土台のしっかりした企画を考えてらっしゃるんだなってのは伝わってきました。

小川:崇弥さん、文登さんの熱い想いのようなものを感じましたか?
板垣さん:うん、うん。熱い想いはもう初対面から、はっきりと感じるものがありました。何があってもひるんだり逃げたりしないんだなって。崇弥さんにとっても未知の部分はたくさんあったと思いますが、不確実なことに向かって挑戦して、それでもなお引き下がらないんだろうなという覚悟のようなものは、最初から伝わってきたと思います。信じるに値するものを何か持ってらっしゃるなっていう感じはあったと思います。
崇弥:ありがとうございます。
小川:そのときは崇弥さんは25歳とか26歳ですかね?
崇弥:そのぐらいですね。よく覚えてるのは、当時は朝6時から会議を毎週やってて「こんな企画書を作って、るんびにい美術館に持っていこう」みたいな話をクリエイターの仲間と一緒にやっていまして、るんびにい美術館に提案し行ったら、美術館側から3名の方に対応していただいたんです。板垣さん以外のおふたりはちょっと懐疑的な部分があったんですね。「正直、これはどうなんだろう?」って感じだったんですけど、板垣さんが「私はこの熱量に賭けてみたいと思います」とコメントをしてくださったんです。当時の自分にとって、背中を押していただいた印象深い思い出ですね。
小川:その板垣さんが賭けた熱量っていうのが、5周年を迎えたヘラルボニーでどんどん大きな形になっていますね。その変遷を見られていて、どんな思いですか?
板垣さん:出会った最初に感じたことに、やっぱり間違いなかったんだなと感じた年月だったかなと思います。熱量がすごいっていうのは、パワフルにグイグイ押してくるような印象ではなくて、崇弥さんって、本当に初対面のときからそのままずっと穏やかなんですよね。穏やかで、こちらの話にも注意深く耳を傾けて、しっかり一言一言を受け止めて。その中にはやや批判的なコメントもあったと思うんですけれども、決してその耳を塞いだりせず、静かで穏やかだけど、間違いなく強くて熱いものが、その奥から伝わってくるような気配だったんですね。それが最初に賭けるに値すると思わせてくれた。とてつもなく大きいエネルギーだったんだなっていうのを、まざまざと見ていったような感じですね。
小川:もちろん崇弥さんと文登さんも、すごい熱量持って臨んでいたんだと思うんですけど、それをちゃんと見抜いて一緒に歩んでこられた板垣さんたちも素晴らしいですね。
#命の気配を感じる場所
小川:ところで、るんびにい美術館自体は歴史的にはどのような歩みをされているんですか?

板垣さん:美術館は2007年11月にオープンしまして、美術館元の法人自体は今から約55年前に設立されました。障害がある児童の入所施設からスタートした法人でその後、昭和40年代ごろに成人の入所施設などが整備されました。
小川:へぇ〜!
板垣さん:そういった事業から始まって、グループホームを作ったり、就労支援センターを作ったりと展開する中で、2007年に美術館というちょっと思い切った、社会福祉法人の事業としては、かなり踏み込んだ事業に取り組み始めたという流れです。
小川:もともとグループホームをやっていたときから、アートの活動みたいなのはけっこうあったんですか?
板垣さん:ちゃんとやり始めたのは、1998年ごろ、私がるんびにいに関わり始めた時期からですね。
小川:美術館の前から板垣さんはいらっしゃったんですね。
板垣さん:美術館ができるちょうど10年ぐらい前から関わり始めました。陶芸活動はその10年ほど前から始まってたのですが、今とても脚光を浴びてる八重樫季良さんや佐々木早苗さんといった方々の作品は、施設ではほとんど注目されておらず、関心を持たれていない存在でしたね。
小川:そうだったんですね。そこから誰かが目を留めてそして美術館を作ろうっていうのは、どういう流れがあったんですか。
板垣さん:当時成人の入所施設の施設長で、今は法人の理事長の三井(みい)さんっていう方がいて、焼き物を始めた人でもあるんですけども、三井さんは八重樫さんたちの絵を見て「よくわからないけど、これらの絵は只者ではないんじゃないだろうか」と予感していたようですね。でも、三井さんも他の職員も、そういったものを評価するはっきりした価値観を持ってなかった。誰かそれを見極められる人間を入れたいと思ってた矢先に出会ったのが、私だったようです。私はちょうどそのころ大学で美術をやっていて、卒業後は無職の「自称美術家」っていう、ニートですね(笑)。バイトもしてなかったので。私、大学にふたつ行ったんです。最初は心理学を4年間やって卒業して、1年フリーターやって、その後また大学に入って4年間美術やって、長いモラトリアムを過ごしてからニートになったっていう。施設長の三井さんは、実はお坊さんでもあって、僕の実家の菩提寺の副住職でもあったんですね。「檀家の家に、なんか心理学と美術を勉強して、今は何もしてない息子がいるらしい」と聞いた三井さんからうちの父親づてに「手伝わないか」と連絡が来まして。「お寺のお掃除のバイトかな?」と思って行ったら、施設に案内されて「あ、施設のほうだったんだ」っていうのが出会いです。
小川:なんか今思えばまさに適任ですし、天職のような感じがするんですけど、最初にその施設に行ってアートをご覧になったとき、どんな印象でしたか?
板垣さん:本当に衝撃でした。うん。私、知的障害のある人とそれまで接点らしい接点がなくて、会話したこともなかったんですね。遠くから見たことがあるとかぐらいしか。どっちかっていうと懐疑的で、あまり関わりたくないとか、そういう否定的な価値観の偏見を持ってる方の人間だったんです。それが思いがけないきっかけで知的障害の方々がいる施設に初めて行って、まずそこにいる方々の温かさにびっくりしたんですね。私が勝手に思ってた知的障害のある人たちのイメージとまったく違いました。私はなにを勝手にイメージを作ってたんだろうと思いましたね。その後に作品を見てもう一度びっくりして。それは八重樫季良さんの作品だったと後にわかるんですけど、ものすごく複雑で、ふたつの構図と美しい色彩の作品があって、それは会話もままならない人が描いているという。そういったすごく個性的な作品を、一人ひとりそれぞれ全く違う表情で描いていて、世界がひっくり返るような衝撃を受けました。

Kiyoshi Yaegashi「(無題)(家)」
小川:八重樫さんは線と丸で部屋の間取りのような、ステンドグラスのような美しい作品を作られていますよね。
崇弥:そうそう!
小川:美術館を作って、そういう作品たちをみんなに見てもらおうと立ち上げたときは、どんな思いで携わられてましたか?
板垣さん:美術館事業という発想は三井さんのもので、私も初めてその計画を聞いたときはちょっとびっくりしたんですけども、社会福祉法人での経験のない私にとっても見当がつかない事業で「なんか面倒くさいころになりそうだな」って腰が引けてたんですけど(笑)。
崇弥:あはは! 思ってらしたんですね(笑)。
板垣さん:ただもうやると決まったからには、自分自身がその意義を信じられる事業にしたいと強く思いましたので、本当に世の中に必要な、この美術館の掲げるべきコンセプトって何だろうと考えて、単に知的障害のある人の作品を伝えるとか楽しんでもらうとかではない施設が必要じゃないかっていう気がしたんですね。美術館のあるべき形とは単に作品の魅力を伝えるものではないはずだという直感的なものを感じて、じゃあ一体なんなんだと。知的障害のある方々の社会的な立場が弱かったり低かったりするという課題は、どこから生まれてるのか根本的な理由を掘り下げて考えていくと、「社会のありふれた一人ひとりの命は平等じゃない」って実は思ってるんだということに行き当たったんですね。「命はみんな平等」だとか「命に差はない」っていう言葉はたくさん聞くんですけども、裏を返せば、そういうふうに何度も何度もスローガンとして掲げなければ、私たちは自然にそう思うことはできないってことだと思うんですね。本質的に違いはないはずなのに、どうして私たちは、命に軽いとか重いとか、大事とか大事じゃないとか、違いを与えてかたくなに守ろうとするのか。ここを解きほぐして「やっぱり命は同じなんだ」とわかるようになれば、知的障害があるからって差別されたり、蔑まれるってことはなくなるはずだし、命の重みづけから生じる不当な差別や排除の根本な原因解決へ近づくことができるんじゃないかと思っていますね。なので、作品を通じて、命の働きとか気配とか、命そのものっていうのを感じさせる美術館をコンセプトにしようと思いました。
崇弥:なるほど。
小川:たしかに、八重樫さんや黒丸の作品で有名な佐々木早苗さんのアートって、本当に命のエネルギーが放たれてますよね。

Sanae Sasaki「(無題)(丸)」
板垣さん:うん。人間の頭や知識でこしらえたものではなくて、人間の生きている中心部分にある、何かど真ん中からのエネルギーが形になって表れた作品なんだなっていう、とてつもない説得力があるんですよね。
崇弥:私も一番最初に見たとき、すごく印象に残りました。やっぱりこのぐるぐるが連なって作品になってるんだと。社会的な承認欲求とかではない、本人たちの強烈な何かから生まれてるんだろうなと感動したのを未だに覚えてます。
板垣さん:うん、もう言わずとも伝わってきますよね。美術が好きな人じゃなくてもわかる。
崇弥:だから、自分たちはそういった作品とご一緒させていただいている以上、その作品の純度そのまま保つことは難しいと思うけれども、最大限近づけて発信しなきゃいけないし、美化するのではなく、ダイレクトに伝えていくことをもっと意識しなきゃいけないと思います。
小川:たしかに。原画からプロダクトにしていくときって、そこのハードルがけっこうあったんじゃないかなと思うんですけど。
崇弥:そこで言うと、一番最初にネクタイを作ったとき、まさにその作品の純度をそのままにどう落とし込んだらかっこいいんだろうと考えて。シルクで織りのネクタイだったら最高にかっこいいんじゃないかと作ってるってところがありました。でもやっぱりね、売れ筋な商品とか手に取りやすいものとか、会社として挑戦していくうえではいろんな選択肢がある中で、初心に立ち返るきっかけをもらうようなお話だなと思って聞いてました。
小川:今はるんびにい美術館で、ヘラルボニーの作家さんの展示を常設されているんですか?
崇弥:いまはるんびにい美術館に所属する作家さん以外の作品も、よく展示をしていただいてます。例えば西成地区の作品とか、障害のある人のアートに限らず、ホームレスの方々だったり、医療的ケア児の方の作品だったりも展示をされていらっしゃいます。
小川:なるほど。ヘラルボニーの所属の作家さんの展示をしたり、逆にるんびにいで出会って、ヘラルボニーに所属される方もいらっしゃったかと思います。今までのるんびにい美術館との関わりで、思い出深いことはありますか?
崇弥:一番最初にるんびにいさんとご一緒できてよかったなと強く思っているのは、板垣さんから「条件があります」と言われてまして。「これからヘラルボニーは、いろんな福祉施設といろんな形でやっていくと思うけれども、作家さんの承認を丁寧に取る会社であってほしいんだ」という言葉をいただいたんですよね。初期のタイミングで。
小川:承認っていうのは、作品を商品化するにあたってのことですよね?
崇弥:まさに商品化だったりまち作りだったり、いろんな形で展開していくときに、作家さんと親御さんと福祉施設さんの三者確認を挟んでいるんですけど、作家さんが金銭的な対価を得て、世に発表されるとか、新聞に出て社会的承認を満たすとか、それがいいことだと一方的に思ってしまうのは、ある種の暴力性があるんです。
小川:そこに作家さんの意思がなくなってしまう。
崇弥:そうです。作家さんは「うん」と言ってるけれども、本当にそれは「うん」なのか。そういうところまでも含めて、丁寧にやってほしいと言っていただいたのは、会社にとって大きな指針になっています。すごくありがたい機会だったなと思います。
小川:本当に大事なことですね。板垣さんは何かヘラルボニーと思い出深いエピソードはありますか?
板垣さん:さっき、最初に作ったネクタイをシルクの織りで作ったという話がありましたけど、私は当然プリントで作るんだろうと思ってたんですね。だけど出来上がってきたのを見たら織りの、しかもシルクだったという。もう本当に衝撃的でした。間違いなく、物体としてものすごく美しいものだったんです。後から話を聞いたら、シルクの織りを引き受けてくれる工場がほぼ全くなくて、ことごとく断られていたそうで。それどころかプリントですら断られてたってね。

崇弥:そうなんです。色数が多すぎるって!
板垣さん:プリントで断られたのに、シルクの織りは譲らないっていう、その胆力というか、そして出来上がったものが本当にもう、衝撃的に美しかった。虹色に光る昆虫の甲羅のような、信じがたい美しさでしたね。しかも、ただ作品の色合いを糸の色で再現しただけじゃなくて、織りという表現で、どうしたら作品の翻訳として最も原画の魅力を活かせるのかが入念に考え抜かれていたんですね。
八重樫道代さんの作品にはたくさん黒い線が引かれているんですけど、その黒の部分だけが少しだけ生地がくぼんでるとか、線で区切られた色と色の境界の縁だけ、太さを変えてるのかな、ちょっと反射率が違ってたりとか。もう尋常じゃない、結晶のようなものができて「これからすごいことが起こるぞ」と思ったんですね。あの最初のネクタイは衝撃的でした。

Michiyo Yaegashi「ワープロ」
小川:その原画がプロダクトになるまでに、あいだに何人も人が入って伝言ゲームみたいになってくわけじゃないですか。それでも美しいものができるって、もとの思いがどれだけ明確で、力強いかっていうところですよね。
板垣さん:そうですね。それに対する高い技術とセンスを持った技術者の方々が本当に全力を尽くして作ったものなんだなと、その出発点が崇弥さんや文登さん、メンバーの方々の思いなんだなっていうことに、心を打たれるものがありましたね。
崇弥:当時ネクタイは文登が担当だったんですけど、エクセルでリストを作って上から順にパーっと電話をして製造先を探していて。色数が多くてプリントすら難しいと言われる中で、あるネクタイメーカーさんから「銀座田屋」なら、世界一のクオリティだから技術的にはできると思うと言われて。調べたら山形県の米沢市に工房があると。でも、製造のOEM(他社ブランド製品の受託製造)請負なんて100年以上の歴史で1回もやってなかったので、これは難しいだろうと思ったんですね。で、ダメ元で文登が「銀座田谷のファンなんです!」って米沢の工場見学させてもらって、私が作った企画書をもって「実はこういうネクタイを作りたくて」と伝えたら、面白いって工場長が言ってくれて。そこから繋いでいただいた銀座の本社でも共感していただいて、100年以上の歴史の中で初めて自社以外のブランドに卸すというのを今もやっていただいています。
小川:すごいなぁ。道を切り拓き続けてる。
崇弥:あれは本当にありがたいきっかけだったなと思いますね。
#ビジネスとして挑戦する覚悟

小川:るんびにい美術館って、2階がアトリエになってるんですよね? ちょっとそのアトリエのお話も聞いていいですか?
板垣さん:ヘラルボニーの商品でもご存知の方が多い、佐々木早苗さんや小林覚さんが活動しているアトリエです。メンバーは現在10人ぐらいですね。その日によって顔ぶれや人数は変わるんですけども。コロナが流行してからは長らく止まっていたんですが、もともとはすごくオープンなアトリエで、階下で展示してる作品を見たり、あるいは1階のカフェで食事やお茶をしてる人が「2階のアトリエも見学できるんだって」「じゃ覗いていこうか」なんて気軽に階段を上がっていくと、もう作者の方たちが描いてたり、居眠りしてたり、何もしないでぼんやりしてたりするっていう空間でした。どなたでも自由に入れて、作者の方たちと自由におしゃべりしたり、気に入って何度も来て顔なじみになったりとか、なんていうか、出会いの場所だったんですね。やっと今、少しずつその状態に戻りつつあるんですけども。昔からある施設って、町外れや山の近くに建っていることが多いんですね。るんびにい美術館を運営する法人の入所施設もそう。ですので、外の世界との交わりはものすごく制限されていました。その点、住宅街のど真ん中にあるるんびにい美術館って、いろんな人が自由に出入りできて出会いを楽しめる、そういう場所なんです。
小川:立地とか美術館のつくりも、そういう出会いの場所を目指して作られたんですか?
板垣さん:実はそうではなかったんですよ
小川:そうなんですか?
板垣さん:そうなんですよ。そもそも建物は新築ではなくて、もともとは陶器の販売をやっている店舗と事務所が入った2階建てビルだったそうなんです。そこが店を閉めて売却に出たものを取得してリフォームしたのが、るんびにい美術館なんですね。
崇弥:当時は最先端の施設で、いろんな方が視察に来たっておっしゃってましたよね? 1階にベーカリー
やカフェがあって、2階がアトリエになっていて、1階に美術館があって。斬新な展開ですよね。
板垣さん:うん、うん。そこに何かしらコミュニティ的な交流が生まれるように狙った構成になってるんですよね。そこは三井さんの構想ですね。すごくそこは的確に捉えていたなと思います。
崇弥:私も実は先週、まさに日本の福祉施設の始まりとなったコロニーを訪れまして。山の中で千人以上の障害のある人たちが共同生活をするための施設だったんです。ちょっと説明すると、福祉施設制度もない時代に、親御さんたちが「全国重症心身障害児を守る会」を結成し、子どもたちを国として救ってくれと訴えていたんです。そこで当時画期的だった、「終身保護」というある程度の年齢になったら施設で生涯を過ごすという福祉の考え方に基づいた国立のコロニーができました。その後、脳性麻痺を持つ方々の当事者団体から「ずっとコロニーで暮らすべきではない、街に出ていくべきだ」という運動が始まって、そこから制度や法律も変わっていったという流れがあるんですよね。だから、甲子園にも出てる花巻東高校の練習樹の真横にあるるんびにい美術館なんて、当時はびっくりされたんだろうなと。
板垣さん:そうですね。やっぱり花巻では住宅街に福祉事業所があるという前例は少なかったと思いますし、まだまだ抵抗を覚える方もいたと思います。同じ法人のグループホームが住宅街にできたときも、やっぱり隣の家の方がすごく不満を口にされていたこともありましたし。「隣に障害者のグループホームができて私の人生は終わったと思ったわ」って言われたことがあります。そういう価値観がまだまだ普通に身近な当時においては、いろんな意味で先駆的な拠点だったとは思いますね。
小川:住宅街の中にるんびにい美術館ができて、街の変化などは感じましたか?
板垣さん:近隣の街については、変化はすぐに感じられなかったです。むしろ、オープンして最初の何年間かは、離れたとこから来る人のほうが多かったという記憶ですね。開館当時から今に至るまで、ずっと常連さんで来てくださる近所のお琴の先生もいらっしゃるんですが、はっきり目に見えた広がりっていうのは、意外と足元の方がすぐには進まなくて。花巻から電車で30分ぐらいの盛岡から来る方の方が多いような何年間かが続きましたね。本当にすこしずつ、いろいろ芽吹いていったような感じですね。
小川:コロナによる自粛が緩和されつつあって、るんびにい美術館も以前の様子を取り戻してきている状況だと思うんですけど、どんな雰囲気ですか?
板垣さん:以前はいろんな方との出会いがあったのが、コロナが大流行してぱったりとなくなり、空気が流れなくなったような、部屋の時間の流れが止まったような、年配のメンバーの方は認知症になっちゃうんじゃないかなと思うような。変化にとぼしかった時間がやっとまた動き出して、皆さんの生き生きした表情がだんだん戻ってきてるかなっていうところです。
崇弥:すごい楽しい場所なんですよ。なんか「X」のバッテンのポーズで握手されるタカハシさんとか、近所のベーカリーまでの地図を何回も描いている方とか、アンポさんって猫のものまねをしてくださる方とか、契約してる作家さん限らず、誰もが来るとワクワクするような空間ですね。
板垣さん:うんうん。みんな本当に笑顔になるし、心がホカホカするし。「元気になりたくてまた来ました」っていう方もけっこう多いんです。
小川:いい場所ですね! 本当に今日はたくさん話し聞かせていただいてとても面白かったんですが、最後にヘラルボニーに対してこんなふうになっていってほしいとか願っていることとか、ありますか?
板垣さん:さっき崇弥さんがおっしゃってましたが、作者ご本人の承認を得るという、ある意味ビジネスとしては、かなり無理のある条件を承諾されて、ちゃんと仕組みの中に入れて、ずっと続けてくださってるというのは非常に大きいと思っています。作品を二次利用として提供する場合って、一般的には著作者人格権の放棄のような不行使特約を結ぶのが一般的なんですよね。「作者はいっさい文句を言いません。自由に使ってください」という契約です。私たちがふだん目にしているデザインものって、ほぼほぼそうなってるものが多いはずなんです。そこをあえて、作者さんが少しでも実感が湧くように「こういう企画です。こういうイメージで、こういう場所に設置されます、ここで販売されます」と、伝え方を工夫しながら毎回確認して、作者さんが納得した上で進めるという仕組みを実装してくださったんですね。こういう分野でのビジネスモデルとして、先駆的事例であり成功事例をヘラルボニーさんがずっと示し続けてくださってるのは、そのこと自体がすごく重要なメッセージになっていると思います。このメッセージをこれからもずっと伝え続けていただけると思うので、その影響というのは大きいだろうなと。もう一つは、今はある種の才能や特別さとして、知的な障害のある方々の存在の社会的評価を高めている最中だと思う
んですけれども、それが虚像化しないように事業展開をしていただきたいなと。ヒロイックなわかりやすいストーリー性に人の価値を当てはめて伝えることで、人間の実存よりも虚像が普及するような流れに陥らないように気をつけていただけたらなと思います。作者さんをわかりやすいストーリーや意味に簡単に落としこんだり、何か特別さという付加価値によって高めるたりではなく、ひとりの人間が生きる価値そのものを、最終的にはしっかり世の中の人たちが認識できるようなところまで持っていっていただけたらなと期待しています。そのためには私もできる限り協力をしていきたいと思ってます。
小川:ありがとうございます。崇弥さん、いかがですか?
崇弥:本当に気が引き締まるお話をありがとうございます。私自身も、4歳年上の兄貴がどれだけ楽しく過ごせるのかがすごく大事なので。会社として投資を受けて、売り上げをどんどん上げていかなきゃとか、もっと挑戦して頑張らなきゃみたいな、ひたすら走り続けるなかでも、大切にしたい価値観を見続けないといけないんですよね。それって、すごく難しいなと。でも、わかりやすくカテゴライズされ、一緒くたにされやすい可能性があるからこそ、兄の松田翔太の息遣いだったりだとか、佐々木早苗さんがいつも履いてるキティちゃんサンダルだったりとか、なんていうんだろう、本当にひとりひとりの姿を大切にしていかなければいけないんだと、あらためて感じました。ありがとうございます!

板垣さん:ありがとうございます。本当に難しい挑戦だと思うんです。知的障害のある方だけじゃないんですけども、障害のある方がなぜ社会の中で低い位置づけにあったり、置き去りにされるかというと、まさに経済性が原因だと思うんですね。
崇弥:そうですね。
板垣さん:その本丸である経済原理の真っ只中に入っていって、否定を肯定にひっくり返す挑戦なので、いろんなトラップがあると思うんです。すごく幻惑されるようなトリッキーな罠が。それはヘラルボニーさんの挑戦のなかで、幾度も起こると思うんですね。でも、崇弥さんと文登さんが率いるヘラルボニーは最終的に突破していけるはずです。だから、その姿を見たいですね。
崇弥:ぜひ一緒にやらせてください! ありがとうございます!
小川:ありがとうございます。板垣さん、るんびにい美術館のお知らせなどはありますか?
板垣さん:福島県に住んでいた大関小夜子さんという脳性麻痺の女性の方の新しい企画展が始まります。病院と施設で、もう一つの自由な自分の人生、あるいは憧れを込めた膨大な数の絵を残している方なのですが、その作品の一部とともに、大関さんの人生を紹介します。2023年9月15日から2024年1月22日まで、4ヶ月ほどの長い展覧会になります。
小川:今のお話を聞いただけで、絶対に見に行きたいと思いました! ありがとうございます。
板垣崇志 Takashi Itagaki

1971年、岩手県花巻市で農家の長男として生まれる。マンガ家を目指した少年時代、脳の認知機能の研究から銅版画に転向した大学時代を経て、1998年に軽い気持ちで地元の障害福祉施設ルンビニー苑の門をくぐることに。(少年時代、その施設名は仲間内で蔑称だった。)そこで暮らす方たちと、その方たちが生み出した造形作品に出会い、人生の流れが変わる。以後、同苑を始めとする福祉施設や支援学校などで知的な障害・精神の障害と共に生きる方々の造形表現の支援に取り組み続ける。同苑運営法人の美術館設立計画に携わり、2007年開館と同時に「るんびにい美術館」アートディレクターに就任。かつて自分はなぜ、知りもしない人たちを蔑んだのか。その問いから出発し、他者の心に出会い、あらゆる命の等質性を体感する場としての美術館づくりに打ち込む。2016年、知的な障害のある人が講師を務める出前授業の普及を目指す、であい授業プロジェクトをスタート。それらの実践をさらに拡張するため、2020年「しゃかいのくすり研究所」を設立。
『HERALBONY TONE FROM MUSEUM〜聴く美術館〜』は無料で配信中

「アートから想像する異彩作家のヒストリー」をコンセプトに、アートに耳を澄ませながら、作品の先に見えるひとりの”異彩作家”の人柄やこれまでの人生に触れる番組です。
役者・映像作家・文筆家として活躍する小川紗良さんと、ヘラルボニーの代表取締役社長の松田崇弥の2名がMCを担当。毎回、ひとりのヘラルボニー契約作家にフィーチャーし、知的障害のある作家とそのご家族や福祉施設の担当者をゲストにお迎えしています。
毎週日曜日にApple Podcast・ Google Podcast・Spotify・Amazon Musicで配信中です。
バックナンバーも無料でお楽しみいただけます。
Apple Music
https://podcasts.apple.com/us/podcast/heralbony-tone-from-museum/id1685097107
Google Podcast
https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/fd66b293-a5b5-4130-a17d-aa9b4d17205b/
Spotify
https://open.spotify.com/show/6FJMpnEDUKhLp3mQx5di4R
Amazon music
https://music.amazon.co.jp/podcasts/4ad5185c-ae0b-4ccc-9fac-f4017f14c8ef/heralbony-tone-from-museum